

1999年3月17日(水)ルーヴェン レコーディング2日目
7時に起床。ホテル0階(ベネルクスのホテルはイギリスと同じで1階は0階だ)で朝食。小さなホテルということもあって食事は質素だけれどさすがにチーズとハム類が美味い。特筆すべきはパン。私が泊まったホテルの朝食には必ずゴマのパンがあった。これがとにかく香ばしくて美味い。φ(^_^) 日本ではひょっとすると「ベルギーの食べ物=ワッフル」みたいに思われることがあるが、私が泊まったホテルの朝食にワッフルを見ることは一度もなかった。(^-^;)
午前中はフリーなので街を散歩することにした。まずルーヴェン駅へ。ルーヴェンはとても小さな街だけれど駅舎はなかなか立派だ。駅前の広場が工事中だったのが残念。


駅前のプレス・ショップでタバコと鉛筆と色鉛筆とクレヨンとベネルクスの地図を買う。タバコは昨日ハーデルマンに教えてもらったバストス、鉛筆はヨメさんへのお土産。ヨメさんは私が出発前に「何でもない文房具が欲しい」と言っていたのだ。ベネルクスはダイヤモンドが有名だけれど、そんなものにはとんと興味がない。安上がりなヤツ。(^-^;) 色鉛筆とクレヨンは子供へのお土産。地図は地理フリークの酒井 格へのお土産だ。
ベルギーの物価はおしなべて日本と同程度と感じる。ただしタバコは高い。バストスは1箱25本入りで138BF(約460円)だ。つまり1本あたり18円。しかも短い。日本のたいていのタバコは1箱20本入りで250円だから1本あたり12.5円。そのせいかベルギーでは日本のように半分くらい吸って捨ててしまう人なんていない。お金持ちでもフィルターギリギリまで吸うのだ。
ボンゲノーテン通りを歩いてルーヴェンの中心部へ。

 上を拡大→
上を拡大→ 
ルーヴェンの市庁舎(写真左)はヨーロッパでも随一とも言われる名建築である。写真でその美しさとスケールの大きさを表現しきれないのが残念だ。そして市庁舎の向かいには聖ピーテルス教会(写真中央)がある。すごく立派な教会だ。てっぺん(写真右)には鐘があって金色の人形が叩いて時を告げる。
 さらに散歩を続けて手芸屋さんを発見。ニットが趣味のヨメさんへのお土産を買うことにする。ベルギーはボビンレースの発祥の国だから何でもいいから買ってきて欲しいとヨメさんに頼まれていたのだ。私は編み物の知識がぜんぜんないし、店員さんの英語もたどたどしく(私はもっとたどたどしく)コミュニケーションに苦労する。なぜか「レース」は通じても「ボビンレース」という言葉は「知らない」と言われた。本場ブリュージュからは少し離れているからかな。それとも単に私の発音が悪かったのか。(?_?) いずれにしてもボビンレースのグッズは見あたらない。普通のレース編み用の針と糸とクロスステッチでキーホルダーを作るキットをいくつか買う。
さらに散歩を続けて手芸屋さんを発見。ニットが趣味のヨメさんへのお土産を買うことにする。ベルギーはボビンレースの発祥の国だから何でもいいから買ってきて欲しいとヨメさんに頼まれていたのだ。私は編み物の知識がぜんぜんないし、店員さんの英語もたどたどしく(私はもっとたどたどしく)コミュニケーションに苦労する。なぜか「レース」は通じても「ボビンレース」という言葉は「知らない」と言われた。本場ブリュージュからは少し離れているからかな。それとも単に私の発音が悪かったのか。(?_?) いずれにしてもボビンレースのグッズは見あたらない。普通のレース編み用の針と糸とクロスステッチでキーホルダーを作るキットをいくつか買う。
 さらに歩くと広場に出た。向こう側には荘厳な建物。何かと思って近づいてみると、大学の図書館
(The Central University Library)
だった。大阪音大の図書館とは格が違うなぁ(ため息...)。
さらに歩くと広場に出た。向こう側には荘厳な建物。何かと思って近づいてみると、大学の図書館
(The Central University Library)
だった。大阪音大の図書館とは格が違うなぁ(ため息...)。
ルーヴェンは学園都市だから若者が多く活気がある。街を歩く人たちにも洗練された気品の高さを感じる。ブリュッセルからそう遠くはないのだけれど、治安は間違いなく日本のたいていの都市より良い。すっかりルーヴェンを気に入ってしまった。
高さのある建物がたくさんあるのでつい視線は足下からはずれる。石畳で足をくじいてしまった。昨日の犬の糞に続いて私の左足は受難続き。(;_;)
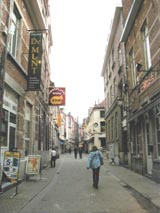 昨日ヤンと一緒に魚料理を食べたレストラン街に行く。市庁舎の裏側にあたる場所である。ここには中華料理、メキシコ料理、インドネシア料理など世界中の料理がある。こんなに小さな街にこんなにたくさんのレストランがあって大丈夫なんだろうかと思うくらい。ベルギー人には美食家が多いといわれるが、なるほどと思った。ちなみに写真の赤い看板には「鉄板屋」と漢字で書いてある。結局入らなかったけれど中華料理が大きな鉄の皿で出てくる店のようだ。
昨日ヤンと一緒に魚料理を食べたレストラン街に行く。市庁舎の裏側にあたる場所である。ここには中華料理、メキシコ料理、インドネシア料理など世界中の料理がある。こんなに小さな街にこんなにたくさんのレストランがあって大丈夫なんだろうかと思うくらい。ベルギー人には美食家が多いといわれるが、なるほどと思った。ちなみに写真の赤い看板には「鉄板屋」と漢字で書いてある。結局入らなかったけれど中華料理が大きな鉄の皿で出てくる店のようだ。
イタリア料理店に入る。一人でレストランに入るのは初めてだ。ペンネアラビアータとスパ(水)とコーヒー。味は...うーん、悪くはないが辛さと酸味のバランスがちょっと酸味にかたよっているような...。日本のイタメシ屋のほうが美味いな。
公衆電話から家に電話。私は「こんにちは」、ヨメさんは「こんばんは」。奏愛は無事に今日幼稚園を卒園したと聞く。感動的な修了式だったのだそうな。行きたかったな。奏愛は周囲に「おとうさんは今寝てるの」と言っていたのだそうな。ヨメさんは「ヨーロッパにいるとは言わないから恥ずかしかった」と。(^-^;)
午後1時にヤンがホテルに迎えに来るのでホテルに戻る。ヤンはまた少し遅刻(20分ほど)。レコーディングは2時から。


金管が疲れないうちに「ババ・ヤガ」と「キエフの大門」を録ってしまおうということで、今日は「ババ・ヤガ」から開始。順調に進む。
「ババ・ヤガ」の Tempo I の寸前の低音楽器のバランスがイマイチ。ホールに行っていろいろ実験をさせてもらうことに。ヤンのアイデアでコントラバス・クラリネットとコントラバスーンを1オクターブ下げるととても不気味なサウンドになった。(^-^;) 「Sehr Good!」思わずドイツ語と英語のチャンポンを発してしまったら一同爆笑。(^○^)
「キエフの大門」のラストのチャイムは私の希望で2台用意してもらった。しかし効果は今ひとつだった。そこでチャイムを2階席に持ってあがって左右に配置し、それぞれにマイクロフォンをセットしてもらった。彼らは嫌な顔をしない。むしろ楽しそうだ。感謝。


試しに叩いてもらう。ホール内はまるで教会のよう。ピアニストがメンデルスゾーンの結婚行進曲を弾く。一同大爆笑。(^○^) こうしてレコーディング・セッションは和気あいあいと進む。
今度はステレオ効果満点。(^-^;) 満足である。5時に「キエフの大門」を録り終えて5人でヤンの車に乗ってルーヴェンの街まで夕食に出かける。
 夕食はスペイン料理。私はベーコン入りのタリアテッリと白ワイン。いずれも美味い。φ(^_^) ワインはドイツワインだったのかな? 甘口で渋みが少ない。ハーデルマンはスペインに別荘を持つほどのスペイン好きなのだと聞く。
夕食はスペイン料理。私はベーコン入りのタリアテッリと白ワイン。いずれも美味い。φ(^_^) ワインはドイツワインだったのかな? 甘口で渋みが少ない。ハーデルマンはスペインに別荘を持つほどのスペイン好きなのだと聞く。
支払いはヨスが持っていたデ・ハスケのクレジットカードで。一同で「サンキュー・デ・ハスケ!」。
7時からレコーディング再開。「古城」の後の「プロムナード」「チュイルリー」「ビドロ」「プロムナード」「卵の殻をつけたひなどりのバレエ」「サミュエル・ゴールデンベルクとシュミュイレ」「プロムナード」「リモージュ」と、一気に進む。
「ビドロ」は低音の和音のバランスが難しい。意図的に連続5度を作った箇所が思った音にならない。ホールに行ってヤンに「バランスと音程をチェックして欲しい」と言ったら「トオル、振ってみて」。そうしてレメンス音楽院シンフォニック・バンドへのミニ・バンド・レッスンとなった。突然のことで学生たちの表情は緊張気味。しかし彼らの反応はすこぶる良く、すぐに良い響きになった。頭が良いんだろうな。
高橋版「展覧会の絵」の「リモージュ」の前の「プロムナード」はチャイムのソロで始まる。最初は堅いハンマーが使われる。「堅くないハンマーで、かつフォルテが欲しい」と言ったがまだ思い通りの音にならない。「聖ピーテルス教会の鐘のように厳かに力強く」と言ったら思い通りの音になった。(^-^;)
ヤンが学生たちに「明日も順調なら明後日はオフになる」と学生たちに告げたらしい(フラマン語だからわからない)。学生たち大喜び。
 休憩時間に学生たちがモニタールームにやってきた。彼らも満足そうである。マルダインにシャッターを切ってもらったが左側が欠けてしまった。左に見える腕はハーデルマンの腕。(^-^;)
休憩時間に学生たちがモニタールームにやってきた。彼らも満足そうである。マルダインにシャッターを切ってもらったが左側が欠けてしまった。左に見える腕はハーデルマンの腕。(^-^;)
ハーデルマンに彼のトロンボーンとテープによる作品を聞かせてもらう。コンテンポラリーな曲だ。テープはこのモニタールームに置いてあるローランドのシンセサイザーで作ったのだそうだ。日本に紹介されているハーデルマンの作品は軽めの音楽が多いが、実はそればかりではない。シリアスなものも少なくないのだ。彼の視野の広さに驚く。
ちなみに彼はたいへんな機械好きである。私もまたオーディオマニアでガラードの1961年製のプレーヤーやクォードのプリアンプやタンノイのスピーカーを使っていてパワーアンプは自作の真空管式の物、そして私も学生時代にローランドのシンセサイザーを使ってクラリネットとテープの音楽を作ったと言うと「全く同じ趣味じゃないか!」と意気投合。
10時前に終了。フルートの学生が楽譜を持って私のところにやってきた。「このシノハラという作曲家のカスガというタイトルの意味を知りませんか?」と。「春日」と漢字で書いてやって、「春」は "Spring" 「日」は "sunshine" の意味。「カスガ」は地名にもあり名字でもあり得る美しい名詞だ、と説明してあげたら「すべての疑問が解けました」ととても喜んでくれた。
昨日と同じ店へ。またドゥヴェルを飲む。( ^_^)/□☆□\(^_^ ) ハーデルマンの家系はおじいさんの代まではドイツだったのだと聞く。それゆえ "Haderman" ではなく "Hadermann" なんだそうな。
実は昨日から彼のドイツなまり(それも古風なドイツ語の響き)の英語のヒヤリングに苦心していた。たとえば "wonderful" は「ヴォンデルフル」( r は巻き舌)だし、"month" は「モンス」だ。スペルを連想しながら聞けばよいのだと頭ではわかっていてもなかなか慣れなかったのだ。さすがに2日目となると彼の英語も聞き取れるようになってきたが、なるほどそういう理由でドイツなまりなんだなと理解できた。
車の話になる。ヨスは自分用のレコーディング機材を積み込んだキャンピングカーをお持ちである。写真を見せびらかして褒めることを強要する。(^-^;) マルダインはいつもガールフレンドに携帯電話で呼び出されてホンダで迎えに行くんだそうな。日本で言うアッシー(死語?古語?)だな。ハーデルマンはルノーのワゴンだ。「私はレクサスES300に乗っている。ヨメさんもトヨタに乗っている」と言ったら「リッチだなぁ!」と驚かれる。ヤンは「トオルの車に乗せてもらったことがある。トオルは日本では本当にリッチなんだ」。ヨーロッパでは日本車は高価なのだ。少なくとも私の旅行中には、日本の小型車はしばしば見たもののレクサス(日本でのセルシオ、ウインダム、ソアラ)はほとんど見ることがなかった。「私にはベンツやルノーは高くて買えない。同じだよ」と言ったらみんな納得。
レメンス音楽院の他の先生も飲みに来る。ピアノの先生と仲良くなる。彼はつい最近もC.H.シュトックハウゼンの作品を弾いたし、「ラプソディー・イン・ブルー」も弾いたのだそうだ。視野の広い人だ。
視野といえば、ハーデルマンは「ベルギーでは視野の狭い人が多く、音楽のジャンルにこだわる人が多い」と嘆く。「いや、日本もまったく同じだよ」と言っておく。
ヤンにホテルまで送ってもらう。ドゥヴェルが効いてぐっすり寝る。(-_-)゜zzz
3月15日(月) ブリュッセルへ
3月16日(火) ルーヴェン レコーディング初日
3月17日(水) ルーヴェン レコーディング2日目
3月18日(木) ルーヴェン レコーディング3日目
3月19日(金)その1 ルーヴェンからコンティッヒのヴァン・デル・ローストの家、アントワープへ
3月19日(金)その2 ブリュッセルでギデ吹奏楽団を鑑賞、アントワープへ
3月20日(土) アントワープからアムステルダムへ
3月21日(日) アムステルダム
3月22日(月)その1 アムステルダムからヘーレンフェーンのデ・ハスケ本社へ
3月22日(月)その2 ヴァン・デル・ローストの家へ
3月23日(火) ブリュッセルから日本へ